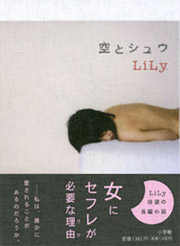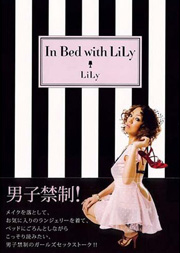2006.03.28 Tuesday
自由って一体なんなのさ?

今日も元気に仕事してたんだけど、
帰りにコンビニでいちごホイップさんどを買うときに、
レジのおじさんにおつりを渡されて、
その指が温かかったことに超泣けて。
(↑すごい病んでるでしょ。笑)
今自分がとっても切ない時期を過ごしているんだなって
はっきりと分かった気がした。
(だから、昨日の日記にみんながくれたコメントが、
とっても嬉しくて、余計にココロにしみた。本当にありがとう!)
だから、小説を書いた。
書かなきゃいられなかったから、
頭に浮かんだストーリーを書きなぐるように、
4時間で書いた。
是非読んでね。そして感想教えてください。
まだまだ小説は初心者マークなので。
多分3日くらいで消すと思うけど。笑
HPの方にも、以前アップしていた
ストリッパーの小説「SIXSEXFOX」を
短編に編集したものを再度アップしました。
↑こちらは超R指定なので、気をつけてね。
今売ってる「HONEY GIRL」に、
連載小説も載っているのでそちらもよろしく♪
このお話はフィクションです。
*******************************
忘れられたターコイズブルーと、
飛べないアゲハ蝶。
By LiLy
********************************
「これなあに?」
「これはね、ちょうちょだよ」
「どうしてちょうちょがここにいるの?」
「ここにとまってるんだよ」
「どうしてとんでいかないの?」
「とべないからだよ」
「どうしてとべないの?」
* ************************************
針が、早いスピードで私のやわらかい肉をチクリチクリと突き刺し続けている。鋭い痛みに、私の神経が小刻みに震える。テーブルの上に乗っけた両手の拳を握り締める。上の歯で下唇ををかみ締める。熱くない、透明の、感情を含まない涙がツーっと目の端から少量流れる。針の動きが止まり、私は深いため息をつく。両手を広げると、手の平が汗でじっとりと気持ち悪い。
「今から、色いれていくからね」
「あと5分、待って下さい。一服してもいいですか?」
彫り師の男は、椅子から立ち上がって奥の部屋へのそのそと歩いて行った。男の筋肉質な上半身に張り付いたランニングの白が、やけに白くに見えるのは、男の首から手首までみっちりと彫られた真っ黒い墨のせいだろう。瞬時に私は、男に猛烈な憧れを抱き、そうはなれない自分をとても愚かに感じ、男へのあまりの嫉妬心に、心臓が止まりそうだった。額に落ちてきた前髪を指でかきあげると、さっきかいた汗が既にクーラーの風に冷やされて、髪の毛がじっとり冷たくなっていた。煙を吸い込む気分にもなれず、私はぐったりうなだれた。自分で自分に怪我させといてなんだけど、太ももの付け根の肉があまりに痛い。傷口をみると、赤く腫れた白い肉の真ん中で、未完成のアゲハ蝶が、私の血にまじってもがいている。
「おまえもきっととべないよ。」
私は意地悪く静かに呟く。
あぁ、今からまたここに、針を突き刺すのかと思うと、気が遠くなりそうだ。男が入っていった部屋のドアが、開かなくなればいい、と思いながら後ろを振り向くと、ちょうどドアが開き、男が出てきてしまった。
「ターコイズブルーでいいんだよね?」
私が自分で持ってきたアゲハ蝶の絵が書かれた紙きれを、男から渡させる。そこでは、色鮮やかな蝶が自由に美しく舞っている。
「痛っ」
男が、私の黒いライン状の蝶の上に滲んだ血を、ティッシュでふき取っていた。
「やっぱり色は、黒で。お願いします」
電気で動かされた針の激しい振動音が、鳴る。あまりの恐怖に、私は体中に鳥肌を立てる。私は再び目を閉じて、拳を握りしめ、歯を食いしばる。
ジーッジーッ。針の電動音。ソワーソワー。上下しながら冷気を吐き出すクーラーの音。
連続する、鋭すぎる痛みの15分間。
真っ暗な視界の中で、私はひとり、涙にならない涙を、流しまくっていた。すぐにココロの器からあふれ出し、下へ下へとこぼれ落ち、体中の全ての内臓をびしょびしょに濡らしてしまう位、大量に。目からこぼれない涙というものは、じっくりと時間をかけて胸を真っ二つに切り裂いてゆく。深まりゆく罪悪感と共に、数ヶ月間かけて、じわじわと割れていった私のハートが、遂に、完全に切り離される瞬間をどんよりとした意識の中で感じていた。太ももの肉が感じている肉体的な痛みが、私の精神をギリギリのところで救った。もしそれがなかったら、私は、ハートがちぎれた瞬間に発狂し、心臓が破れ、死んでいたことだろう。
針が肉から抜かれ、ジーッという音が止まる。
**********************************
目を開けて、ヒリヒリと私を痛みつけているところを見ると、そこには真っ黒なアゲハ蝶が、私の足にしがみつくようにしてとまっていたよ。私は自分で犯したあの罪を、自分の体に痛みを与えて罰することで、少し救われるんじゃないかと思ったんだ。そして、自分の体にこの墨を彫り刻むことで、自由になれない自分が、少しは自由になれる気がしてたんだ。だけどね、こんな小さくて、こんな可愛い蝶々なんかじゃさ、何も変わらなかったよ。逆に、自分の中途半端な自由思考をね、この墨は私の体にしっかりとね、刻んでしまったんだよ。左の骨盤のすぐ下の、太ももの付け根なんてね、どんなに短いミニスカートでも隠れるんだ。もし男にそれを剥がされた時だってね、こんな小さな蝶々なら、大して引かれることもないんだわ。プールにも、温泉にだって、入れるしね。なんてったって、明日の朝から、また普通に会社に出勤できるんだ。墨ってより、単なるファッションだよね、こんなもん。どんなに、どんなに、自由に羽ばたくことに憧れていたって、結局私はこんな風にして、毎回、飛べない。今私から5万円を受け取った男みたいには、なれないんだ。私はさ、世の中で幸せだと呼ばれるものだけを、幸せなんだと思い込んでいる、ちっぽけな女なんだってば。だって、あと50時間くらい歯を食いしばり続ければ、男と同じような体になれるんだよ、私だって。いっそ、そうできたら、どんなにいいだろう。首から手首までの肉の隅々に黒いインクを流し込む、その勇気が私にあれば、よかったのに。50時間後、新しい体を手に入れたら、私は真っ先に、タケの元に走ってゆくよ。タケにもう一度会えるなら、あの痛みに耐えることくらいなんでもない。
嘘。やっぱり私には、できない。だから、殺した。
**********************************
男の店を出て、巣鴨の駅まで歩く途中に、ごちゃごちゃした商店街を通った。そこは、ばあさん用の洋服とか、じいさん用のせんべいとか、とにかく、世の中に老人と呼ばれている人が好みそうなもの全てが、ここに集められて売られているような、そんな通り。次々に視界に入ってくる、生活感剥き出しの原色が目に痛かった。その道は、私を苦しませた。晴れた空も、夏という季節も、私にとってはたまらなく残酷な昼探り。
* **************************************
タケはいつも、私が今まで目にしたことのないような色を作り出した。タケの描く絵は、タケのココロん中とおんなじ匂いがした。それは、暖かくて、なんだか懐かしくて、湿っていて、だけどなんとなく気だるい、梅雨が明ける前の、春でも夏でもない中途半端な一日の匂いに似ていた。付き合い始めた二十歳の頃、タケの絵が売れないたびに、私はほんのり嬉しかった。その匂いを嗅ぎ分けられるのは、世界中で、タケと暮らしている私一人なんだって思えたから。タケと一緒に住んでいた吉祥寺のアパートは、ドアを開けるたびに絵の具と油の匂いがした。すぐに鼻が慣れるから、すぐにその匂いは消えるのだけど、靴を脱ぐまでの数秒間だけ感じることができるその匂いを、私はとても愛していた。タケと私は5年間、毎日その部屋で一緒に眠っていた。小さなベッドの横には、いつもスケッチブックがあった。寝る前に5分、と時間を決めて、タケは、化粧を落とした後の私の素顔を絵に描いた。毎晩、描いた。タケは、私の顔は毎日違うと言った。忘れたくないから、描きとめておきたいと言った。でも私はよく、タケより先に眠ってしまった。起きると、必ず、スケッチブックには、私の寝顔が描いてあった。だから、多分私は世界で一番自分の寝顔に詳しい女になった。私はたまに、小さく口をあけて眠る。私はたまに、眉間に皺を寄せて眠る。だけどほとんどの夜は、安心しきった赤ちゃんのように平和な顔をして眠っていた。
タケの絵が売れないことに、私がちっとも喜びを感じられなくなったのは、私が大学を卒業して就職した年からだ。その日のことをよく覚えている。私は二十三歳になったばかりの6月で、タケは三十歳になっていた。ある夕方、私は営業先を次から次へと回っていた。アポイントの時間に遅れそうで、私は焦っていた。重いカバンと、着ているだけで疲れるスーツと、ハイヒールで地下鉄を乗り継いで、階段を何段も何段も掛け上がって、やっと地上に出ると、外は雨が降っていた。電車に傘を置いてきてしまったことに気付いた時、私はその時に匂った梅雨の匂いを憎たらしく思った。その瞬間から、私はタケの絵を愛せなくなった。それからは、あんなにも愛おしかったタケの色も、玄関の匂いも、ただただ私を苛立たせるだけだった。それでもそれから二年間、私がタケの隣で生きていたのは、ほかでもない。タケとの永遠を手に入れたかったから。タケ以外の男に触れられることさえ、私には考えられなかった。タケへの愛とタケからの愛を失ったら、私もタケも死ぬって本気で思っていた。もし私がタケの子供を産んだらなら、タケは毎日毎日その子の絵を描くだろうなって考えた。何度も何度も、三人でいるところを想像した。タケはきっと、惜しみない愛情を、私と子供に与え続けてくれるだろうな。タケと一緒にいて私が幸せなの、誰よりも私が一番わかっていた。
それでも私がタケを捨てたのは、私の心が感じていた確かなものよりも、世の中で確かだと言われているものを、選んだからからなんだ。二十五の梅雨が来る前に、私は殺した。タケと私の間の愛と、二人で夢みた永遠を、私は、自分の手で、過去に葬ったんだ。
ひとりで歩く梅雨は、どこにいってもタケの匂いがした。暖かくて、なんだか懐かしくて、湿っていて、だけどなんとなく気だるい匂いを、やっぱり私はたまらなく好きだった。雨に紛れて私は泣いた。梅雨が明けて夏がくる頃には、熱い涙が枯れ果てた。私の中のハートがメキメキ音をたてて割れていく度に、私は大声をだした。
* **************************************
どうしても、
どうやっても、
思うままに、
自由に、
羽ばたくことが出来ないで、
もがいていた私に手を差し伸べてくれた今の旦那は、
初めて私の太もものアゲハ蝶を見たとき、
「かっこいいね」
と静かに言ったんだ。
あんな風にタケを愛しながら、あれだけタケを恋しがっていた私が、歯を食いしばりながら体に刻んだ墨は、自由に羽ばたくことを考えたこともない、地に足のついた男にも好感を持たれるくらい可愛いものだったわけなんだ。中流階級の家庭で育った私には、どんなときでも、頭のどこかが冷静な判断を下すようインプットされてしまっているのだろう。
「この道は安全だからここを歩きなさい」
自由を何より求めながら、それでもその上を歩く自分が、どうしても許せなかった、二十五の夏。
*****************************************************************
「ままのちょうちょおえかきしてもいい?」
四歳になる息子が私に聞く。
手には、黒いクレヨンを持っている。
息子の126色のクレヨンセットの中から、
私はタケのターコイズブルーを探す。
*********************************
このお話はフィクションです